今回は抽象度を上げる方法について。
抽象度を上げると、こういったメリットがあります。
・IQ(知能)が上がる
・物事を俯瞰的に判断できるようになる
・あらゆる問題の解決方法が一瞬で浮かんでくる
・他の人には見えない真実が見えてくる
とは言っても、
「抽象度を上げる」
この言葉、少し分かりにくいかもしれません。
まずは抽象度という言葉の意味を解説

「抽象的」という言葉はあなたも
聞いたことがあると思いますが、
まず、
具体的⇔抽象的
という反対語としての、言葉の対応関係がありますよね。
抽象度というのは、
このような「具体的⇔抽象的」という”軸”があって、
その軸の中でどれだけ「抽象」の方に位置するか、
というのが「抽象度=抽象の度合い」ということになります。
「では抽象度とは何に当てはめられるのか?」
と聞かれれば、その答えとしては、
「抽象度は、あらゆる概念に当てはめられる」
と答えることができます。
たとえば、
「犬」という概念があったなら、
その犬は「ある特定の抽象度」に位置していると言う事ができます。
「ある特定の抽象度」とは言っても、
それがどこにあるのかという「絶対的」な位置を示すことはできません。
逆に「相対的」な位置関係なら示すことができます。
例えば、「犬」に対して「動物」という概念がありますね。

このとき「動物」は「犬」よりも高い抽象度に位置しています。
もう一つ例を挙げてみましょう。
「お茶」という概念(モノ)があったとします。

このとき「お茶」の抽象度を上げると「飲み物」になります。
ここで「犬→動物」の例と
「お茶→飲み物」の例に、共通する法則があります。
それは
「抽象度が上がるとそこに内包される概念の数が増える」
ということです。
これだけだと、まだよくわからないはず。
なので、もう少し詳しく説明してみます。
たとえば「お茶」の例でいうと、
「飲み物」というものは抽象度が高いので、
「お茶」「水」「ジュース」など複数の情報を内包します。
「犬」の場合も、
「動物」には「ネコ」も含まれますし、
「魚」「虫」「鳥」「爬虫類」など様々な概念が含まれています。
(もちろん、さらにこれらの概念同士で抽象度を比べることもできます。)
このように、
「抽象度が上がると下にぶらさがっている概念の数が増える」んです。

そして抽象度を上げるためにはまず、
そのように下にぶら下がっている概念を
知識として覚えることが最低限必要になります。
その上で、それらの知識の共通点を見つけることで、
それら知識の上位概念を見つけ出していく必要があるんです。
これがまず、「概念の抽象度を上げる」ということの意味合いになります。
では
「抽象度はどんな概念にでも当てはめることができる」
ということがお分かりいただけたところで、
「抽象度は人にも当てはまる」
ということを説明していきます。
抽象度は人にも当てはまる

そう、「抽象度は人にも当てはまる」のです。
これは「人→動物」という概念的な意味合いではなく、
「人の思考にも抽象度がある」という意味合いになります。
このときの抽象度の意味としては
「視点の高さ」
とも言い換えることができます。
この視点の高さを上げて、
物事を俯瞰して見ることが(思考の)抽象度を上げるカギになるのです。
物事を俯瞰して見られる人は、抽象度が高くなり、
普通の人に見えない世界が見えてきます。
つまり抽象度の高さが、思考力であり、創造力なのです。
抽象度を上げていくことがそのまま
「頭を良くすること」だと考えていただいて良いと思います。
例えば、「極端に抽象度が低く、目の前の事しか見えていない人」は、
「抽象度が自分より高い人」が、何故、何のために行動しているのかがわかりません。
つまり抽象度が低いと、物事の本質が見えてこないんです。
具体例を挙げると、
ある晴れた日。
抽象度が低い「Aくん」が道を歩いていたとして、
周りの人が、みんな傘を手に持っていたとします。
このとき「Aくん」は
なぜ周りの人が傘を持っているのかがわかりません。
この日は、「朝の天気予報で
降水確率70%の予報が出ていた」のですが、
「Aくん」は天気予報を見るという習慣がありません。
その結果、
「晴れているのに、なんでみんな傘を持ってるんだ?」
という思考になります。

ここで、時間を超えた推論ができれば
天気予報を見ていなかったとしても、
「みんなこれから雨が降ると思っているから傘を持ってるんだな」
ということがわかりますが、
「Aくん」にはそれを考えるには至りませんでした。
したがって
「なんでみんな傘を持ってるんだ?」
という疑問が浮かぶだけでわけがわかりません。
これが抽象度が低い人の一例です。
ただし、抽象度はリアルタイムで変化しますから、
もしAくんが、友達から
「今日は午後から雨が降るらしいよ」
と聞いた時点で、抽象度は周りの傘を持っている人と
同じところまで上がることになります。
ただし、やはりAくんは
「時間(と空間)を超えた推論」ができないので、
また同じような疑問に何度も突き当たるはずです。
このように抽象度が低いと、
物事の本質に気づけなかったり、
そもそも目の前で何が起こっているのか分からなかったりします。
したがって、抽象度を上げることが重要なんですね。
では、その重要性をご理解いただけたところで、
ここからは、抽象度を上げるトレーニングを見ていきます。
抽象度を上げるトレーニング
抽象度を上げるトレーニングはいくつかあるので、
様々な角度からアプローチしていくのが有効です。
そうすれば柔軟な思考力が手に入れる上でも役立つはず。
ではまず1つめの方法。
目の前のものを一つ次元を上げてみる。

まず一つ目です。
その方法とは、
日常で目に映ったもの何でも良いので、
何かの物体を、抽象度を一つ上げて見てみるということをしてみてください。
目の前の物の名前が頭に浮かんだら、その認識を一つ抽象的に変えてみるということ。
たとえば、
・コーヒーを飲むとき、カップをカップとしてみない
⇒食器として認識する・ネコと遊ぶとき、猫を猫として見ない
⇒動物として認識する・空を仰いだ時、太陽を太陽として見ない
⇒宇宙として認識する・クルマに乗るとき、車を車として見ない
⇒乗り物として認識する。・電話をするとき、携帯電話を携帯電話として見ない
⇒通信機器として見る・本を読むとき、本を本として見ない
夢を叶える脳力トレーニングより
⇒印刷物や出版物として見る
これらは本質を確認するということにもなります。
その物体の本来の機能を考えることが、自然と抽象化につながると思われます。
ここで、抽象度を上げて物を見るための簡単な方法をお伝えしたいと思います。
それは、
「○○という名前がついているけど、本当は何かの分類の一つだ」
と考えることです。
「目の前に置いてあるものは何の種類に当たるのだろう」
そう考えることで、抽象度の高い見方が自然と出来るようになるでしょう。
このとき、抽象度を一気に上がらないようにすると、より良いトレーニングになると思います。
たとえば、
ネコ⇒ネコ科⇒哺乳類⇒脊椎動物⇒生物
というように段階を分けることも出来ます。
ちなみに分類の仕方をさらに細かく分けると、界・門・綱・目・科・属・種のように複数あるため、抽象度はもっと細かく階層分けできます。
ちょうどいい抽象度を探ることも良いトレーニングになるでしょう。
言わば、抽象化とは物事を統合して見ていくこと
であり、
具体化とは物事を分割して見ていくことだとも考えられます.
さらに抽象度を理解するために、具体化についても考えていきましょう。
今度は具体化のトレーニング
スイス人言語学者フェルディナン・ド・ソシュールは、
「まず最初に抽象化された世界があって、そこに言語が生まれたことで神羅万象が見えるようになるのだ」
ということを主張しました。

これは、言葉が存在する前に物事や観念は存在しない、ということです。
かなり抽象度が下がりますが、
具体例を出してみます。
たとえば、「弁当大好きBくん」が昼食に駅弁を食べるとしましょう。
Bくんは、昼に特急に乗りながら、そこで駅弁を食べた後、
夜にセブンイレブンに足を運び、そこでコンビニ弁当を買おうとして迷いつつ、
「まあ駅弁とコンビニ弁当は全然違うからいいか。」
という気持ちでコンビニ弁当を夕食にします。

一方で、アメリカ人で、日本のことをよく知らないし、
弁当になじみがない「Mr.C」(Cさん)を呼んで、
同じように昼に駅弁を食べて、
夕食にセブンイレブンのコンビニ弁当を食べてもらいます。
このとき恐らくですが、
アメリカ人のCさんはコンビニ弁当が出てきたときに
「昼もランチボックスだったのに、夜も似たようなランチボックスだな~」
と思うかもしれません。
これにはいくつか理由があるはずですが、
まずは、
「弁当の違いが見分けられないので同じ弁当に見える」
ということが言えると思います。
もっと詳しく言うと、例えば
「同じような醤油味のおかずばっかりじゃないか」
とか
「またライスが入っているよ」
などと考えてしまう可能性がるわけです。
(ちなみにCさんは正直なだけで、性格の悪い人ではありません。)
ただ、「同じ食べ物に見える理由」は、
それよりももっと単純なところにあります。
それは
「”駅弁”と”コンビニ弁当”という言葉を知っているか否かの違い」
です。
ランチボックスという一括りにしている状態と、
”駅弁”と”コンビニ弁当”で分けて覚えている状態では、
その弁当に対する「認識」自体が変わってきます。
言葉を知っていることで別物だと認識できるのです。
言葉を知らない人からしたら全く違う2つの事象が、
その言葉を知らない人が見れば同じものに見えてしまう。
つまり言語は世界を分割し、形作っているのだといえるのです。
別の例として、今度は反対に英語を見ていきましょう。
たとえば、「牛」という単語。
これを英語では、雌牛はcow、去勢した雄牛をox、去勢しない雄牛をbull、子牛をcalf、といったように別の単語で使い分けます。

日本語ならオスの牛、メスの牛というように、牛という一単語で表すのに対し、
英語ではそれぞれに固有の単語が与えられているのです。
つまり日本人ならば同じ牛として見ている動物を、
英語圏の人々は全く異なる4種類の動物として見ているということになります。
弁当と牛の例のように、
言葉は現実を分割していくという性質を持っているということです。
つまり、名付けの役割の1つは「具体化」であり、
具体化とは、抽象度を下げて細分化していくことになります。
ただ、名付けは「抽象化」としても利用できます。
これは矛盾しているように見えますが、
言語は一定範囲の抽象度をまたいでいるのです。
これを分かりやすくするために、
「言語」を抽象度の軸で表すと、
具体的 ⇐ 中間 ⇒ 抽象的
物理空間 ⇐ 言語(情報の一部)⇒ より抽象度の高い情報
といったように、言語が
抽象度としては中間に位置していることがわかります。
(あくまでも大体のイメージですが。)
つまり物理空間より情報空間の方が
抽象度が高いということであり、
さらに情報空間の中で下の方に「言語」が位置している
ということになりますね。
もう一つ具体例を挙げると、
「数字」なんかは情報空間の中でも、
より抽象度が低く、具体的であると言えます。
例えば、リンゴの大きさを、
「こぶし大の大きさ」
と言葉で表現するより、
「4.6cm3の体積」
と数字で表現した方が具体的ですよね。
(前者の表現だと、その重さは「こぶしと言う言語」の抽象的な基準に依存しています。)
このように、「数字」が情報の中でも比較的、抽象度が低い方だということが
お分かりいただけたはずです。
ただ一方で、
「言語より抽象度が高いものがあるのか?」
という疑問もあるかもしれません。
言語そのものが、
現実世界(物理空間)を「抽象化」するツールなのですからね。
ただ、言語より抽象度が高いものは、
結論から言うと、あります。
例えば、「愛」という概念は、
「愛」という「言語」があるにせよ、
その意味合い・概念そのものは
言語だけでは表せませんよね。
言い換えると、言葉で愛を定義することはできません。
したがって「愛」という概念は
情報空間において、かなり高い抽象度に位置していると考えられます。
このように、言語より高い抽象度の概念も存在します。
ただし、そこまでいかなくても、
「言語」だけでも結構高い抽象度には位置していることも事実。
ということは言葉を上手く扱えるようになることは、
ある程度の範囲内で、抽象度を自在に操る訓練にもつながります。
言葉によって作り上げられる世界のことを、「言語空間」と呼ぶなら、
この「言語空間」の抽象度は、現実世界(物理空間)よりも、
比較的高いところにあると言えるのです。
したがって、目の前の事物や概念を
「言語化」
することで、言語空間に入ることができ、
それこそが抽象度を上げるトレーニングになるのだということもできます。
つまり「言語化」や「言語を扱う事」が
具体化のトレーニングになると同時に、
抽象度を上げるトレーニングにもなるということ。
したがって、
まずは言語空間の中で、できるだけ上に上がっていくことが、
抽象度を上げる上で有効な手段だと言えるでしょう。
では言語空間に入り、その中で情報を理解・思考する技術を
上げるためには何をすればいいのかというと、
それは簡単で、本を読めば良い、ということになります。
読書する

ここまで
「抽象度を上げる」
方法論について述べてきました。
この考えのもとになった人物は、苫米地博士という方ですが、彼は一日3冊の読書を推奨しています。
3冊だとどうしても難しい場合は最低でも一日1冊は読んでほしいとのこと。
上で述べたように、言語が世界を作るという性質を持っている以上、
言語空間を広げていくことが視野を広げ、抽象度を上げるための土台作っていきます。
さらに本を読んでから、その内容について自分なりに批評・考察してみたり、
思考を巡らせたりしてみることで、言語空間における知識の操作能力が上がっていきます。
どんな本を読めばいいかというと、
ジャンルを限定せずに多読するべし、とのこと。
興味がない分野も読むことで、視野が広がり創造的な思考力が鍛えられていきます。
本を読んだ後は、どうしてこの本がベストセラーになったのか考えてみても良いでしょう。
そうすることで、思考力の訓練になります。
本の優れた点や、世の中の需要を複合的に考えることで
広い視野でものごとを考えられるようになるのです。
これにより抽象度は上がっていきます。
ちなみに読書というのは他にも、
・ストレス解消効果が科学的に証明されていたり、
・共感力が上がって対人関係が改善したり、
などのメリットがある事が知られています。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
↓さらなる読書のメリットはこちら。






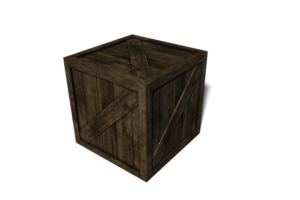

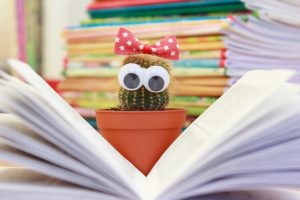




コメントを残す